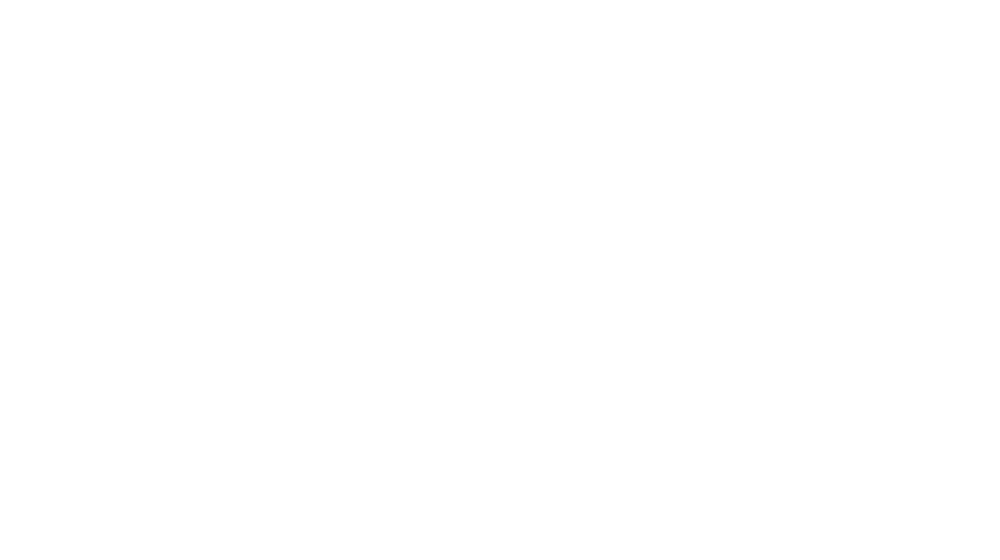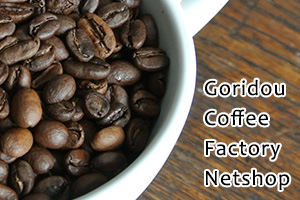本を売ります(その1:どうやったら個人でも新刊本を売ることができるのか?)
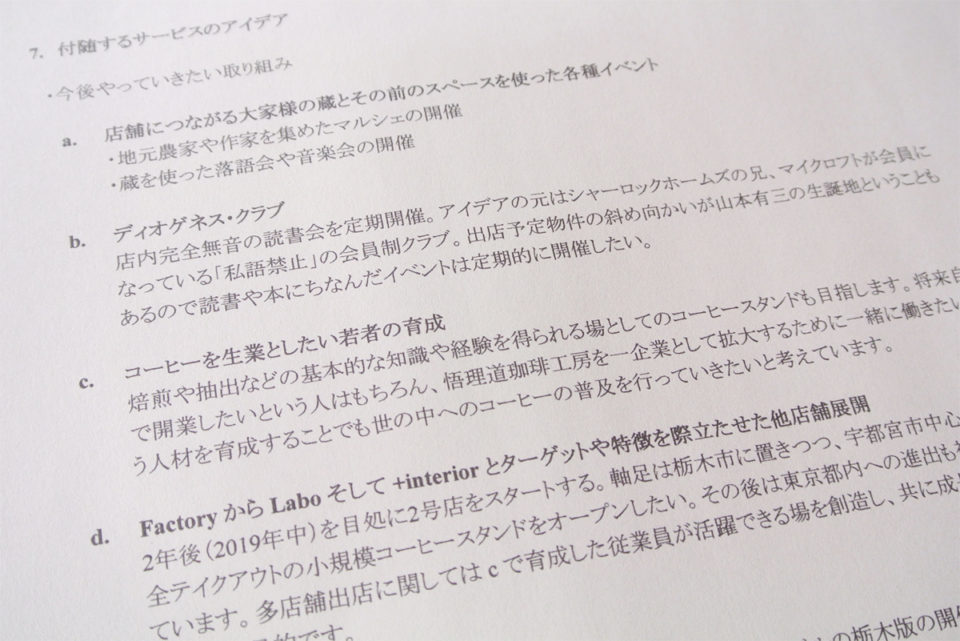
悟理道珈琲工房の新しい試みが近々始まります。その試みとは「本を売る」こと。
本を読むのが好きです。
なかなか時間は取れなくなっていますが今でも好き。高校生の頃は図書館で本を読むことだけが人間性の欠片も感じない日々から逃避できる唯一の時間でした。
というわけで「本屋さん」をやってみたいという気持ちは昔から心の内に秘めて履いたのですが、紙の本を取り巻く状況はここ数年なかなかに厳しい。
インターネットの普及で雑誌が売れなくなり、紙の本を中心とした活字離れが顕著になり、街の本屋さんはどんどん減っていくという負のスパイラル。
そもそも大手の出版取次を介した本の流通経路は個人で新規参入するにはハードルが高すぎ(というか無理)で「本屋さんをつくる」というのは夢のまた夢のような状況です。
そんななか僕が本のためにできることといえば「本を読みやすい環境を作ること」ぐらい。お気づきじゃない方も多いと思いますが悟理道珈琲は案外本をじっくり読むのにいい店内環境づくりを心がけている「本好きの方のためのお店」だったりもします。おいしいコーヒーと本、そしてテクノ(ここは異論がありそうですが)。僕がお客さんなら毎週本を片手に通うこと間違いなし。
という思いで今までも本棚にちょこっとだけ自分のオススメ本を置いて自由に読めるようにしていたのですが、そろそろ次のステップに行ってみようと思います。
それが「本を売る」こと。しかも新刊本の本屋さんを始めます。
前述したとおり新刊本を扱う街の本屋さんは減る一方です。しかも自分のような個人事業主が本屋さんを始めたいからといっておいそれと出版取次と契約できるものでもありません。
そこで見つけたのが出版取次規模全国3位の「大阪屋栗田」が始めたFoyre(ホワイエ)という1冊からでも本を卸売りするサービスです。どのような経緯で始まったサービスなのかというのはFoyerのホームページに書かれた内容を読むのがわかりやすいので引用させていただきます。
現在、出版界を取り巻く厳しい要素は枚挙に暇がありません。そのひとつが、例えば新しいメディアの台頭です。もし私たちの感情がシンプルであるならば、それこそがテクノロジーの進化であるとして、この状況をあるいは前向きに捉えるべきなのでしょう。ただ、どこか、茫漠とした寂しさがあります。本当に終わりなのでしょうか。
一方で、このごろ、本屋さんではないお店で本を見かけることが多くなりました。カフェで、アパレルショップで、雑貨店で。そのお店では本たちが、コーヒーや、シャツや、食器と、あまりにも違和感無く同居しています。お店を魅せる役割を果たしています。そしてそのお店に立ち寄るお客さんは、手に取って、とても熱心に紙の本を眺めています。
出版界の衰退が叫ばれる中、「本」に、確かに新たな居場所ができつつあります。それはともすれば、ずっと昔からあったのかもしれません。そしてその居場所の存在に気づかなかったことが、「本」の可能性を狭めてしまっていたのではないか。そこに私たち、出版取次会社の反省点はないのだろうか。
Foyer【ホワイエ】は、1冊からでも本を卸売りします。カフェの、アパレルショップの、雑貨店の、花屋の、家具店の、スポーツジムの、すべてのお店の、初めての書籍販売をトータルにサポートいたします。システム、物流から選書のサービスまでご提供しますので、本を手軽に、新たな商材として取扱いいただけます。
Foyerホームページから引用
という訳で悟理道珈琲ではこのFoyerのサービスを利用して新刊本を仕入れて販売していきます。
仕入れのルートができたところで、次は「どんな本をなんのために売るのか?」というテーマを決める必要があります。次回はそのへんのお話です。